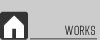第3話 日田杉
3/4
さて、そうしたログ・ハウジング草創期の熱い思いを受けて、今日のログハウス事業は、年間概算150棟もの注文生産を続けているという。取引先は県内はもちろん、九州全域から、関西・関東地方にも至っている。そのログの特長は、なんといってもマシンカット丸ログにサネ加工がなされていることである。しかもこれは、特許取得品となっている。最近は、このグルーブのサネ加工をダブルサネ加工にする機械も開発し、さらにノッチ部分の性能アップを図るために、複雑な断面加工にも着手しだしている。
中津江村にある、それらの丸ログ加工施設をログ・ハウジングの古閑広巳さんに案内していただいた。加工施設は、原木の保管場所から、木材の乾燥場、丸太の荒皮取り、そして円柱加工、丸ログ断面加工までよく整備され、一貫した流れの体制になっている。加工ラインも新旧合わせて3カ所ある。そのひとつの最も新しいラインは、平成10年度の林業振興事業で整備したもので、加工ライン全てがコンピューターによって制御される完全なNC加工ライン。オペレータ一人で、複雑な加工を行ってしまう。校木加工だけでなく、ポスト&ビームのジョイント加工までも行える。マシン加工の精度アップは日進月歩である。もはや、ここまできてしまったという印象であった。
日田ログの強みは、そうした充実した加工ラインと徹底した品質管理にもある。特に最近は、ログ材の乾燥に力を注いでいるという。乾燥は原則として自然乾燥だ。太い丸太は、いったん角材にしてから乾燥させ、その後に円柱加工に入る。乾燥は含水率25%~30%を目標にしており、約2~3ヶ月を必要とする。これまでの2000棟近い実績が、この加工施設の発達した環境に現れている。
日田群には、もうひとつのログメーカーがある。日田群森林組合のログ・ハウジングとほぼ同時期の昭和61年に設立された、蜂の巣ログハウジングである。こちらは、角ログを中心に加工・販売を行っている。校木断面は大・中の角ログと、楕円タイプのログの3タイプあり、いずれもダブルサネをもち、日田杉の40~50年前後の木材を使用している。平成10年に防火性能ログとして建設大臣認定を取得した。今後、本格的な住宅地や市街地内の住まいづくりに営業展開をしていくと、川野幹夫代表はいう。この蜂の巣ログハウジングも、上津江村のログ事業の協力を得て発足したといわれるから、この地域での木材活用は、もとをたどれば、全て上津江村に行き着くようだ。
2、“津江杉の家”づくりと上津江村のトライ・ウッド
トライ・ウッドは、日田マシンカット・ログの発祥の地、上津江村が行っている第3セクターの森林および木材活用の組織である。林業労働者の高齢化や後継者不足、さらには木材価格の低迷といった問題を打破しようと、当時の上津江村の村長・井上伸央氏がスタートさせたと聞く。実際の事業内容は、植林、下刈り、枝打ちなどの森林の管理事業から、加工事業まで多様である。上津江村にある、その加工現場を訪れ、さらにトライ・ウッドによる、村内のいくつかの施設を案内していただいた。
社員50名、今や村の優良雇用の場に成長したトライ・ウッドの加工場では、木材乾燥、木材の難燃加工、板材や角材の徹底した商品管理や津江杉を使った木製サッシの生産が行われていた。そうした木材の商品化の中で、そうした木材の商品化の中で、とりわけ注目したのは、津江杉の活用を図った在来構法による、“津江杉の家づくり”である。省エネルギー、健康、環境共生をテーマに開発され、現在はOMソーラー協会への材料供給
も行っている。
こうした組織の前向きな活動を村や森林組合、他の公益的組織も支援している。ログペンション「丸太ん坊」に始まり、木造の様々な施設、福祉、保健、医療を一堂に集めた村の高齢者福祉センター「上津江診療所」、上津江村立「すぎっこ保育園」……などなど。村内には住宅をはじめ、公共・公益施設の積極的な木造建築化が行われており、それらにトライ・ウッドの材料が使用される。工場だけが充実していても、だめなのだ。木材は、消費者に利用されてこそ初めて生きてくるのだ。