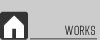第3話 日田杉
4/4
3、木製サッシ、オリジナル家具、エコ建材の開発に見る日田の努力
上津江村を中心にした日田群のいくつかの施設は、それぞれ設計デザインが重視され、構法、空間的にもユニークな建築が多い。さらに、そうした施設に始まり、木製サッシも、津江杉を活用したオリジナル商品なのである。近年、それらに津江杉材による木製家具の開発も加わった。これらの家具もまた、本格的なデザインがなされ、杉のもつ素朴な素材感を生かした、見事な作品として仕上げられていた。
4、 津江杉の磨き丸太は日田林業の誇り
1~3で記述した木材活用は、全てが近代的な設備と、それを支える新しい木工技術者によって生み出されている。磨き丸太は、いってみればその反対の環境の中で生産されていく。機械ではなく、熟練されたベテランの職人さんの腕によることが多いし、森林から立ち木を伐り出すときから、既に注意と技術が必要である。したがって年々需要も少なくなっているのだが、スギ丸太の本当の自然な美しさを伝えるには、磨き丸太が一番であると確信する。その、手間はかかるが美しい磨き丸太を大切にし、今も生産を続けるだけでなく、さらに今日の新しい建築に、それを取り入れ、利用しているのが何よりも素晴らしい。私達が日田郡内で案内されたいくつかの施設の中でも、磨き丸太が輝いていた。
日田森林景観を支える人々の努力と郷土への想い
日田森林環境が生み出している精度の高いログ材の加工技術とその販売体制は、おそらく全国でもトップクラスであろう。そうした校木加工にとどまることなく、在来構法の家から、家具や建具の開発にも力を入れてきている。そうした新しい木材活用の背景に、真っ正面から取り組んできている多くの人々がいることを忘れてはならない。今回の取材中もそうした木材加工にかける方々の熱いまなざしを常に感じることができた。
さらに、今回はお会いすることができなかったが、訪れる場所で必ず耳にした上津江村の前村長・井上伸央氏と、津江川に設けられた下筌ダムの反対闘争に生涯をかけた宮原知幸氏の名は、記憶に深いものがある。
井上伸央氏は、今日の日田ログハウスの基盤を築いた人でもあり、日田の木材活用に大きく貢献してきた人だ。現在もご健全で、県議として、トライ・ウッドの代表として活躍されている方でもある。その実績は前記した通りでもある。
宮原知幸氏は、ダム建設に当たって、湖底に沈む138haの杉の森林と、234戸の村のために、地域を無視した国家権力に対し、全財産と生涯をかけて闘い抜いた人である。彼が反対運動の拠点として築いたのが、急斜面に長さ300mにも及ぶ巨大な砦であり、人はそれを蜂の巣城と呼んだという。この砦に宮原さんは5年近く立てこもることになるが、最後には強制的に取り壊しとなってしまう。今から30年前、昭和39年のことである。宮原さんは、一方的にダム建設に反対したのではない。必要とは思えないダム建設と、環境を無視した上位権力の開発姿勢に対して反対したのであるという。氏の晩年は、地域の発展や観光のためならとして、所有地を提供するが、津江の美林景観を壊すべきではないとの条件をつけ、ダム周辺の道路を、山を削らないよう、トンネルとさせたのだ。一度思い立った信念を曲げないで突き進む。ある意味で頑固者。“肥後もっこす”、九州男児とでもいおうか。そうした強烈な生き様がうかがわれる。その背景にあるのは、誰にも負けない郷土愛であり、結果として祖先から受け継いできた、森林景観、日田杉(津江杉)の美林を想う心なのだろう。井上氏と宮原氏には、そうした根底で深くつながるものがあると余所者の私には感じられた。そうした郷土を想うこと、森林を愛することが、時にはダムの反対闘争のエネルギーになったり、新しい木材活用の事業を成功させる力になっているのだろう。
新しいものを生み出す力と、古いものを継承していこうとする力のバランスが日田にはある。こうした日田林業に学ぶことは非常に多い。それは、21世紀につながるであろう林業の可能性を、森林文化の再構築の灯りを、かいま見る思いがした。